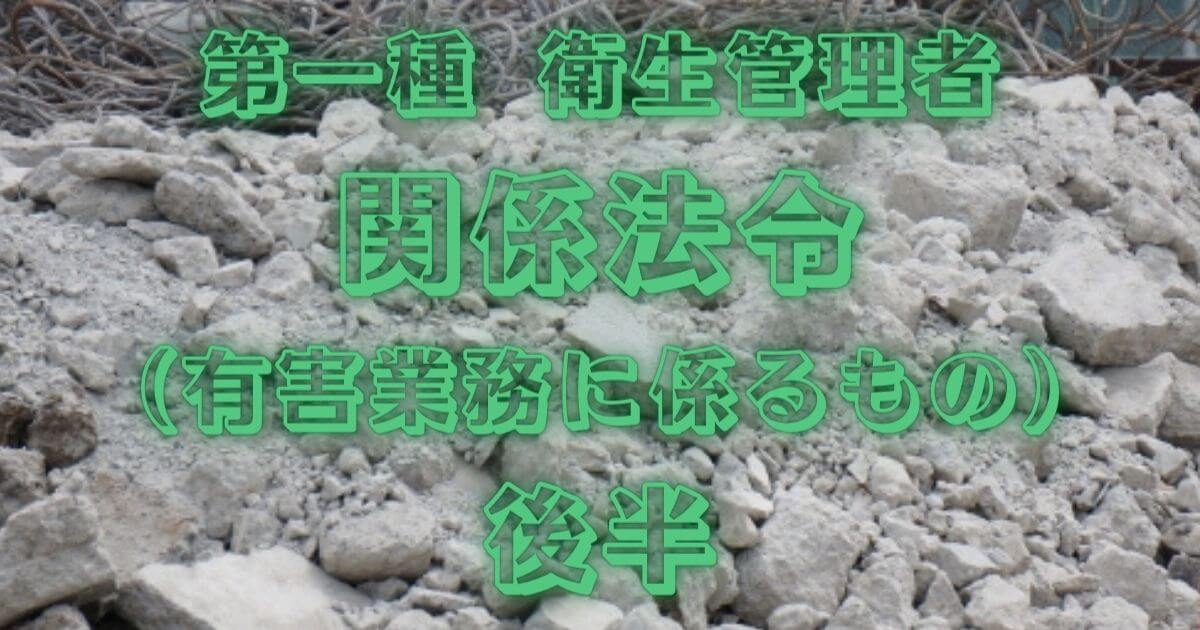このページは第一種 衛生管理者の試験対策のうち、関係法令:有害業務に関わる内容から作業環境測定・定期自主検査・特殊健康診断と健康管理手帳・予防規則と防止規則・労働基準法(有害業務関連)について書いています。
関係法令のうち有害業務に係るもの(後半)です。前半はこちら!
- 作業環境測定と立入禁止場所
- 定期自主検査
- 特殊健康診断と健康管理手帳
- 予防規則と防止規則
- 労基法:女性・妊産婦への配慮
- 労基法:有害業務の残業制限
 おっさん
おっさん…関係法令(有害)の後半戦、やるか。
 でぃでぃ
でぃでぃやりましょう!
衛生管理者-関係法令 有害:作業環境測定・立入禁止場所
【難易度:中】
作業環境測定
立入禁止場所
衛生管理者試験に向けた覚え方
作業環境測定は労働安全衛生法・第二条に定めがあり、定期的に有害物質の濃度などを測り、記録蓄積するというものです。
また、作業環境測定をする「有害な場所」の多くが関係者以外は立入禁止となるので、その整理を見ていきます。
※作業環境測定の測定項目などは、この後の「予防規則と防止規則」と密に関わるので流し流し見ておくのでOKです。
 おっさん
おっさんヤベー場所の状況把握と部外者の立入禁止だな。
作業環境測定の測定項目・測定頻度と記録の保存
作業環境測定については試験でほぼ確実に出題されます。
よくある出題のパターンは測定項目と測定頻度の組合せの間違い探しです。表に纏めてあるものを覚えておきましょう。
| 有害 カテゴリ | 有害な作業内容 環境・場所・設備等 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 放射線 | エックス線照射 ガンマ線照射 | 線量当量率 放射線物質濃度 ※作業環境測定士が実施 | 1カ月以内 | 5年 |
| 酸素欠乏 異常空調 | 酸素欠乏場所 | 酸素濃度 硫化水素濃度 | 毎日 作業開始前 | 3年 |
| 〃 | 坑内作業 | 炭酸ガス濃度 気温・通気量 | 炭酸ガス:毎月 他:半月以内 | 3年 |
| 〃 | 空気調和設備のある 建築物の室 | 一酸化炭素濃度 | 2カ月以内 | 3年 |
| 暑熱・寒冷 多湿 | 暑い・寒い・多湿 | 気温・湿度・輻射熱 | 半月以内 | 3年 |
| 騒音 振動 | 著しい騒音を発する 屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6カ月以内 | 3年 |
| 特化物 有機溶剤 | 特定化学物質 (第1類・第2類のみ) 有機溶剤 (第1種・第2種のみ) | 物質の空気中濃度 ※作業環境測定士が実施 | 6カ月以内 | 3年 |
| 鉛 | 鉛業務を行う 屋内作業場 | 物質の空気中濃度 ※作業環境測定士が実施 | 1年以内 | 3年 |
| 石綿 | 石綿を取扱う 屋内作業場 | 空気中の石綿濃度 ※作業環境測定士が実施 | 6カ月以内 | 40年 |
| 特定 粉じん | 特定粉じん (セメントの袋詰めなど) | 粉じん濃度 遊離ケイ酸含有率 ※作業環境測定士が実施 | 6カ月以内 | 7年 |
| 有害 カテゴリ | 有害な作業内容 環境・場所・設備等 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録 保存 |
作業環境測定は覚え方に悩む内容なので、幾つかの断面で表中の情報を切り出してみます。
作業環境測定の基本から
(基本パターンを軸に考えて覚える)
①測定項目はその有害業務と関連する
・酸素欠乏:酸素濃度と硫化水素濃度
・熱い寒い:気温・湿度・輻射熱
・騒音:等価騒音レベル
・有害物質:空気中の物質の濃度
①測定頻度の基本は6カ月以内に1回
・鉛業務は1年以内に1回
・放射線は毎月
・温度や通気量は半月ごと
②記録保存の基本は3年間
・放射線は5年間
・特定粉じんは7年間
・石綿は40年間
また、特定の有害業務では作業環境測定士が作業環境測定をすると決まっているものがあります。
作業環境測定士が測る
①放射線(エックス線・ガンマ線)
②特化物 第1類・第2類 ※第3類は対象外
③有機溶剤 第1種・第2種 ※第3種は対象外
④鉛業務
⑤石綿・特定粉じん
※作業環境測定士=衛生管理者とは別の資格です。
 おっさん
おっさん地道によく考えながら覚えるしかないか…
 でぃでぃ
でぃでぃ頻出問題なので楽はさせて貰えませんね。
第一種 衛生管理者試験で作業環境測定については問3-問8あたりに高確率で出題されます。
■問.法令の基づき定期に行う作業環境測定とその頻度の組合せで誤っているものは次のうちどれか。
(1)非密封の放射性物質を取扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度:1カ月以内/1回
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベル:6カ月以内/1回
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量:半月以内/1回
(4)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度:1年以内/1回
(5)多量のドライアイスを取扱う業務を行う屋内作業場における気温と湿度:1カ月以内/1回
誤っているものは(5)です。
別パターンで作業環境測定士が作業環境測定をしなければならないものを選ぶ問題が出る事も時々あります。
■問.次の法定の作業環境測定を行う時、作業環境測定士が測定を実施しなければいけないものはどれか。
(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベル
(2)バルブ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素および硫化水素の濃度
(3)有機溶剤を製造する工程で有機溶剤等の混合を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度
(4)溶融ガラスからガラス製品を成形する業務を行う屋内作業場における気温・湿度・輻射熱
(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
対象のものは(3)です。
こちらは1つ目の出題パターンに比べると出題頻度は低いですが、出る時は出るので構えておきましょう。
 おっさん
おっさん出ると判ってりゃ仕込んどくしかねーか。
 でぃでぃ
でぃでぃ作業環境測定は一旦ここまでです!
第一種 衛生管理者試験 論点:立入禁止場所の対策
有害業務の作業場などは、関係者以外の立入を禁止しその旨を見やすい場所に表示しておくと定められています。
これは試験の論点としては非常に簡単なので、条文を読んだ後すぐに試験対策をします。
労働安全衛生規則より引用
第五百八十五条事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十(10ppm)を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
ざっくり要約すると、騒音・振動を除く有害作業場のだいたいが当てはまり、四の酸素欠乏については数値に注意すれば良いです。
 おっさん
おっさん何に気をつければいいか判るとやりやすいな。
第一種 衛生管理者試験で立入禁止場所については問3-問8あたりで出題され、出題頻度は3割程度です。
■問.労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の立入を禁止しなければならない場所に該当しないものはどれか。
(1)多量の高熱物体を取扱う場所
(2)病原体による汚染のおそれの著しい場所
(3)ボイラー製造等、強烈な騒音を発する場所
(4)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
(5)硫化水素濃度が10ppmを超える場所
該当しないのは(3)です。
この問題は難易度が低いですが、出題率も低いので「出たらラッキー」くらいに考えておきましょう。
 おっさん
おっさんめちゃ簡単だ。問1との差は何だよ…
 でぃでぃ
でぃでぃ酸欠の数値は他でも使うので覚えて損はないですよ!
 でぃでぃ
でぃでぃ立入禁止場所についてはここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:定期自主検査
【難易度:高】
定期自主検査
衛生管理者試験に向けた覚え方
定期自主検査も先ほどの作業環境測定と同じく、衛生管理者試験の受験者を悩ませる論点です。
学習が進め辛く悩むのは、関係法令よりも労働衛生っぽい内容で見慣れない装置名や設備名が出てくるからです。
この辺りを消し込んでいくと定期自主検査を攻略する活路が見えてきます。
 おっさん
おっさん何の設備か判んないのをそのままで覚えるも何もないよな。
定期自主検査の対象設備の覚え方
定期自主検査は有害業務を行う作業場に設置された設備の定期的な自主検査です。
自主検査なので誰が検査実施しても良く、実施後に労基署への報告も不要です。(記録は3年保存というルールはある)
定期自主検査の対象となる装置・設備の概要を見てみましょう。
換気・排気装置
1.局所排気装置
有害物質が飛散する作業場で局所的に気流を発生させ、ダクトを通して外へ排気する装置。後述の除じん装置や排ガス処理装置とセットで運用される事が多い。
2.プッシュプル型換気装置
有害物質の発散源を吹出側(プッシュ)と吸込側(プル)のフードで挟んで気流を発生・制御し、有害物質を作業範囲から外に漏らさず換気する装置。
3.全体換気装置
作業場外からキレイな空気を取り込み、作業場内で発散している有害物質を希釈しながら外へ排気する装置。全体換気装置は定期自主検査の対象外である事に注目。
 おっさん
おっさん本当にコレ、労働衛生の方で出てくる内容だな…
有害物質を除去する装置
1.除じん装置
排気中の粉じんやヒュームを除去する装置。粉じん等を発生する有害業務は鉛・特定粉じん・石綿。
2.排ガス処理装置
有害ガスを無害化するための装置。可燃性ガスの安全な処理や悪臭のあるガスの無臭化などもする。ガスを発生する有害業務は主に特化物。
3.排水処理装置
汚水を浄化する装置。汚水を垂れ流す有害業務は主に特化物。
特定の有害業務に関連する設備
1.特定化学設備
特化物の製造および取扱いに関わる設備類の総称。当然のこと関連する有害業務は特化物。
2.透過写真撮影用ガンマ線照射設備
名前の通り。関連する有害業務は放射線。
 でぃでぃ
でぃでぃこれを先に見ておくと、まとめるのが楽です!
装置・設備の種類をざっと見たので、定期自主検査の要否・頻度を表にまとめます。
※縦軸:装置・設備の種類 / 横軸:有害業務と頻度
| 装置・設備 | 特化物 | 有機 溶剤 | 鉛 | 特定 粉じん | 石綿 | 放射線 | 定期の 検査頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局所排気装置 ブッシュプル型換気装置 | 第1類 第2類 | 要 | 要 | 要 | 要 | 1年以内 | |
| 全体換気装置 | |||||||
| 除じん装置 | 第1類 第2類 | 要 | 要 | 要 | 1年以内 | ||
| 排ガス処理装置 排水処理装置 | 要 | 1年以内 | |||||
| 特定化学設備 | 要 | 2年以内 | |||||
| 透過写真撮影用 ガンマ線照射設備 | 要 | 1カ月以内 |
 おっさん
おっさん定期自主検査の頻度は基本が年イチか。
定期自主検査は試験に出ると難しい
定期自主検査について、第一種 衛生管理者試験での出題頻度は高くないものの出題されると難易度は高いです。
一先ず、何も構えずに(攻略法ナシで)でやってみます。
■問.次の装置のうち、法令上で定期自主検査の実施が規定されているものはどれか。
(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(2)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
(4)酸化プロピレンを使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(5)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
…実施が規定されてるものは?
明らかな対象外の2つは(1)・(3)と判ります。
 でぃでぃ
でぃでぃこの後、どーしましょ?
その後の回答の絞り込みは…?
回答に悩む理由と突破口
・残った(2)(4)(5)には特化物の物質名
・局所排気装置は定期自主検査が必要
・プッシュプル型換気装置も定期自主検査は要る
→ 特化物は第1類・第2類が定期自主検査の対象
→→ 第3類の物質を選択肢から除外…?
…少し見えてきました。
出てきた物質名が特化物 第1類・第2類か、それ以外か?というのが判れば何とかなりそうです。
でも、第1類=製造許可物質だから良いとして第2類の物質数が多すぎる問題が…それなら。
特化物 第3類の物質は以下の8つで身近な物質名です。
| No. | 第3類の特定化学物質 |
|---|---|
| 1 | アンモニア |
| 2 | 一酸化炭素 |
| 3 | 塩化水素(塩酸) |
| 4 | 硫酸 |
| 5 | 硝酸 |
| 6 | 二酸化硫黄 |
| 7 | フェノール |
| 8 | ホスゲン |
 おっさん
おっさん第3類の物質名は他の資格とかでもよく出てくるやつだな。
ここで問題にリベンジです。
■問.次の装置のうち、法令上で定期自主検査の実施が規定されているものはどれか。(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(2)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置(3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
(4)酸化プロピレンを使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
(5)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
定期自主検査の対象は(4)です。
 おっさん
おっさん急がば回れ的なのが攻略法なのかよ…
 でぃでぃ
でぃでぃ結果的にそーなりました。
 でぃでぃ
でぃでぃ定期自主検査については一旦ここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:特殊健康診断と健康管理手帳
【難易度:並】
特殊健康診断
健康管理手帳
衛生管理者試験に向けた覚え方
有害業務に従事する人・した人は、その有害業務で起こりうる健康障害について特殊な健康診断を受ける事になります。
また、特定の有害物質に携わった人は「その後、身体の異変は大丈夫?」という健康管理手帳の発行を受けます。
実務目線であれば、有害業務と起こりうる健康障害や特殊健康診断の内容などを包括的に学習したいところですが、見るべき範囲が膨大になるのと…
 でぃでぃ
でぃでぃ…尺の都合というよりは…
…実は、第一種 衛生管理者の試験での出題ポイントはとても絞られているので、試験対策に特化した内容で纏めます。
 おっさん
おっさん試験対策をする訳だから余計なのは一旦置いとくって事か。
特殊健康診断
特殊健康診断は有害業務ごとに実施内容等が定められていますが、実施頻度などは共通点が多いです。
特殊健康診断の共通事項として以下の定めがあります。
特殊健康診断の共通事項
①雇入れ時に実施
②配置転換時に実施
③基本的に6カ月以内に1回 定期実施
④健康診断結果報告書を労基署へ提出
⑤提出タイミングは「遅滞なく」
⑥診断結果表は「●●健康診断個人票」
(↑ ●●には有害業務や物質名が入る)
これに加えて有害業務それぞれに診断項目や記録の保存期間が設定されています。
| 特殊健康診断 | 主な診断項目 | 記録保存 |
|---|---|---|
| 高気圧業務健康診断 対象:高圧室内・潜水 | 四肢の運動機能・聴力・肺活量 尿中の糖および蛋白の有無 | 5年 |
| 特定化学物質健康診断 対象:第1・2種 特化物・製造等禁止物質 | 特化物による ※特別管理物質(ガン原生物質)の記録→ | 5年 ※30年※ |
| 有機溶剤等健康診断 対象:有機溶剤 | トルエン:尿中場尿酸 ノルマンヘキサン:尿中2,5-ヘキサンジオン | 5年 |
| 鉛健康診断 四アルキル鉛健康診断 | 血中の鉛 尿中デルタアミノレブリン酸 | 5年 |
| 電離放射線健康診断 対象:エックス線・ガンマ線 | 白血球数・赤血球数・白内障・皮膚 血色素量またはヘマトクリット値 | 30年 |
| じん肺健康診断 対象:粉じん・特定粉じん | 直接撮影による胸部エックス線 粉じん作業の職歴・肺機能・結核 | 7年 |
| 石綿健康診断 対象:石綿 | 直接撮影による胸部エックス線 | 40年 |
第一種 衛生管理者の試験では表中の有機溶剤等健康診断がほぼ確実に登場します。
 でぃでぃ
でぃでぃ他のも出るけど頻度は低いので浅く広く押さえましょう。
じん肺健康診断
特殊健康診断の中で、「じん肺健康診断」のみ扱いが異なるのでポイントを押さえていきます。
「じん肺健康診断」のタイミング等です。
| じん肺 健康診断 | 実施タイミング等の解説 |
|---|---|
| ① 就業時 | 新たに常時就業する事になった時 |
| ② 定期 | 後述の「じん肺管理区分」により 1年毎または3年毎 |
| ③ 定期外 | 粉じん作業に従事中に 一般健診でじん肺所見有の場合 |
| ④ 離職時 | 1年以上 粉じん作業に従事したら |
主な診断項目は上の表に落とした胸部エックス線や肺に関するものです。
 おっさん
おっさん離職時にも健診やるのは押さえておかないとだな。
表中②で出てきた「じん肺管理区分」は症状の重さなどを4つに区分したものです。
管理区分と診断や状況、事業者がとる措置について纏めます。
| 管理 区分 | 診断・状況 | 必要な 措置 |
|---|---|---|
| 管理 1 | じん肺の所見なし | 特になし |
| 管理 2 | 不整形陰影はあるが、 著しい肺機能障害はない | 粉じんの 曝露低減 |
| 管理 3 | 同上 (程度は管理2より重い) | 同上 配置転換 |
| ※ | 管理2 or 3 + 合併症罹患 | 療養 |
| 管理 4 | 著しい肺機能障害がある | 療養 |
「じん肺管理区分」に関するポイントは以下となります。
じん肺管理区分の要点
・労働者はいつでも診断を受けて申請できる
・診断または審査:地方じん肺診査医 が行う
・管理区分の決定:都道府県労働局長 が行う
・事業者は当該労働者へ遅滞なく通知
・通知の事実を書面に残し3年間保存
・じん肺管理区分2・3の決定を受けると「健康管理手帳」の発行対象となる
※健康管理手帳については後の節で触れます。
 おっさん
おっさんこうやって情報が整理できると理解もしやすいな。
 でぃでぃ
でぃでぃ単独の内容だと整理しやすいんですけどね…
 でぃでぃ
でぃでぃ…衛管の勉強は色々絡み合い過ぎで整理のしかたに悩むのが多い…
試験での特殊健康診断の登場のしかた
特殊健康診断は試験で単独問題はほとんど出ませんが、予防規則・防止規則の問題での選択肢として登場します。
※予防規則・防止規則は後ほど解説します。
■問.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時の洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものはどれか。
(1)作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出せるものとする
(2)作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知る事ができるよう、容器に青色の表示をする
(3)有機溶剤作業主任者に有機溶剤業務を行う作業場について作業環境測定を実施させる
(4)作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行う
(5)作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に有機溶剤等健康診断を行う
(5)が特殊健康診断の内容です。
特殊健康診断のサイクルを問われているだけで、正しくは6カ月以内ごとに1回です。
特殊健康診断と診断項目の組合せで正誤を問われる問題が出る事もありますが、ここで無理して覚えなくても大丈夫です。
 おっさん
おっさん関係法令と労働衛生を一周してまた帰って来いって事か。
 でぃでぃ
でぃでぃそーですね。周回プレイでトロコンを目指す感じです。
 でぃでぃ
でぃでぃ特殊健康診断については一旦ここまでです!
第一種 衛生管理者試験 論点:健康管理手帳
有害業務の中でも特に重度の健康障害を発生する恐れのある物質に携わる人には「健康管理手帳」が交付されます。
健康管理手帳に関するポイントは以下です。
健康管理手帳の要点
・労働者が離職時・離職後に交付申請する
・手帳の交付:都道府県労働局長 が行う
・主な対象:特化物・粉じん作業・石綿
・鉛と有機溶剤は手帳の交付要件ではない
健康管理手帳の交付要件となる有害物質・有害業務を整理します。
| 取扱う物質 有害業務 | 交付要件 (従事期間) |
|---|---|
| ベンジジン ベータ-ナフチルアミン ジアニシジン | 3カ月以上 |
| 1,2-ジクロロプロパン | 2年以上 |
| ビス(クロロメチル)エーテル ベンゾトリクロリド | 3年以上 |
| クロム酸・重クロム酸 塩化ビニル | 4年以上 |
| 三酸化ヒ素 | 5年以上 |
| ベリリウム | 両肺野に慢性の 結節性陰影 |
| 粉じん作業 | じん肺管理区分 管理2・3 |
| 石綿 | 1年以上※ 両肺野に不整形陰影 胸膜肥厚 |
※石綿=1年以上かつ初めて石綿の粉じん曝露を受けた日から10年以上経過している事。
 おっさん
おっさん…とりあえず表の赤字から覚えるか。
過去問を解いて試験対策
第一種 衛生管理者試験で健康管理手帳に関する問題は、取扱う物質または有害業務と交付要件の組合せの正誤です。
■問.次の有害業務に従事した者のういち、離職時または離職後に法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
(1)ビス(クロロメチルエーテル)を取扱う業務に3年以上従事した者
(2)硝酸を取扱う業務に5年以上従事した者
(3)鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
(4)メタノールを取扱う業務に10年以上従事した者
(5)粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理1の者
正しいものは(1)です。
※複数の過去問で何故かビス(クロロメチル)エーテル・3年以上という組合せが正解となっている事が多いです。
 おっさん
おっさん要は対象外の探し方なのか…
 でぃでぃ
でぃでぃ対象外を覚えるという覚え方もアリですね。
 でぃでぃ
でぃでぃ健康管理手帳についてはここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:予防規則と防止規則
【難易度:中】
【重要度:高】
予防規則
防止規則
衛生管理者試験に向けた覚え方
関係法令(有害業務関連)の中間まとめとなる「予防規則・防止規則」を見ていきます。
第一種 衛生管理者試験の問1-問10のうち最低2問は出題され、多い回では4問出題されていました。
 おっさん
おっさん出題数が多いなら「捨て問」にもできないか…
「○○中毒予防規則」や「○○障害防止規則」という名前で有害業務それぞれに定められています。
予防規則・防止規則の構成
(試験対策で押さえる要素)
・その有害業務で特に気をつける事
・その有害業務での基準値や区分
(既出)作業主任者の選任
(既出)特別の教育
(既出)作業環境測定
(既出)定期自主検査
(既出)特殊健康診断
試験の問題では既出の要素を含めての複合問題となっている分、選択肢一つ一つは単純なので、問題慣れしておくのが攻略法となります。
 おっさん
おっさんRPGでいえば、中ボスが色んなタイプの雑魚を引き連れてる感じか…
 でぃでぃ
でぃでぃそのイメージで割と合ってるかもです。
有機溶剤中毒予防規則の攻略
有機溶剤中毒予防規則は、第一種 衛生管理者の試験において毎回出題されています。
有機溶剤について
・他の物質を溶かす有機化合物の総称
・トルエンやベンゼンなど
・普段は液体だが揮発性が高く蒸気となる
・蒸気を皮膚から吸収して健康障害を起こす
・有害性などの序列で第1種~第3種に区分
・第1種~第3種は作業場の色分けが必要
第1種~第3種 有機溶剤と作業場所の表示色
作業場では有機溶剤の区分での色分けが必要です。
| 有機 溶剤 | 表示色 | 物質の例 |
|---|---|---|
| 第1種 | 赤 | 二硫化炭素 ニ塩化アセチレン |
| 第2種 | 黄 | アセトン トルエン |
| 第3種 | 青 | ガソリン 石油ベンジン |
 でぃでぃ
でぃでぃ危険度や物質を作業場所の色で間違えないようにしています。
換気・排気装置と密閉設備
屋内作業場で第1種・第2種 有機溶剤を取扱う場合、以下のものの設置が必要です。
設備の設置基準
(①②はいずれかを設置)
①プッシュプル型換気装置
②局所排気装置
・制御風速(≒吸引力)は0.5m/s以上
③密閉設備
④排気口・排気管等は屋根から1.5m以上に設置
・直接外気に向けて排気する
※第3種 有機溶剤しか扱わない作業場は①②の代わりに全体換気装置の設置でも良い。
 おっさん
おっさんここでも第1種・2種 有機溶剤の話で第3種は一旦スルーでもいいかもな。
保護具・空容器の扱い
プッシュプル型換気装置・局所排気装置・密閉設備のいずれかを設置している作業場では保護具の着用は不要です。
ただし、第3種 有機溶剤を使用する作業場で全体換気装置だけの場合、送気マスク・有機ガス用防毒マスクの着用が必要です。
また、有機溶剤の空容器は蒸気を発散するので、密閉して屋内保管するか屋外の一定の場所に集積しておきます。
有機溶剤関連の既出論点
最後に有機溶剤に関わる既出論点を整理します。
| 既出の論点 | 要否・頻度・内容 |
|---|---|
| 作業主任者 | 選任要 技能講習の修了 |
| 特別の教育 | - |
| 作業環境測定 | 6カ月毎・記録3年 空気中の有機溶剤濃度 作業環境測定士が実施 |
| 定期自主検査 | 1年毎・記録3年 局所排気装置 プッシュプル型換気装置 |
| 特殊健康診断 | 有機溶剤等健康診断 雇入時・配置転換時 6カ月毎・記録5年 主に物質の尿中濃度 |
 でぃでぃ
でぃでぃ試験では既出論点も含む問題が出ます…
試験対策の材料を揃えたので、過去問から有機溶剤中毒予防規則の問題をやってみます。
■問.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として法令上、誤っているものはどれか。
(1)作業場所に設けた局所排気装置(外付け式フード)は0.4m/sの制御風速を出せるものとする。
(2)有機溶剤等の区分の色分けは黄色で行う。
(3)作業場における有機溶剤の濃度を、6カ月毎に1回、定期で測定し記録を3年間保存する。
(4)作業に常時従事する労働者に対し、6カ月毎に1回、定期に特別の項目について健康診断を行い、有機溶剤等健康診断個人票を5年間保存する。
(5)作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年以内に1回、定期に自主検査を行い、記録を3年間保存する。
誤っているものは(1)です。
特定の事柄・基準値+既出論点のまとめで攻略できました。
 おっさん
おっさん特殊健康診断のとこで問題見た時は無理ゲーとも思ったが…
 でぃでぃ
でぃでぃ問題がどの要素で構成されているか判れば戦えますね。
 でぃでぃ
でぃでぃ次は酸欠の防止規則です!
酸素欠乏症等防止規則の攻略
酸素欠乏症等防止規則も、第一種 衛生管理者の試験において極めて高い頻度で出題されています。
呼吸の際、吸い込む空気中の酸素不足であったり硫化水素が含まれていると、頭痛・吐気~脳へのダメージ等の症状が出ます。
酸素欠乏に関する定義などを整理します。
| 定義 | 状況・内容 |
|---|---|
| ① 酸素欠乏 | 空気中の酸素濃度18%未満 |
| ② 酸素欠乏等 | ↑または 空気中の硫化水素10ppm超 (10ppm=100万分の10) |
| ③ 酸素欠乏症 | ①または②により 頭痛や吐き気を認める |
| ④ 第1種 酸素欠乏 危険作業 | ①の場所、酸素欠乏に陥る ・腐泥層に接する井戸の内部 ・ドライアイスを使用する庫内 ・発酵物を入れた槽内 |
| ⑤ 第2種 酸素欠乏 危険作業 | 硫化水素10ppm超の場所 硫化水素中毒にかかる 海水・し尿・汚泥・汚水等を 入れたマンホール・タンク等 |
 おっさん
おっさん酸欠の第2種は硫化水素絡みなのを覚えると良さそうだな。
作業場への入退場と労基署への報告
酸素欠乏危険場所での対応と措置
・労働者が入場または退場する際に人数確認
・作業場には避難用具を用意
・冷蔵室の室内作業等の場合は出られなくなる事のないよう措置を講じる
・酸素欠乏症等が発生したら労働基準監督署長へ報告
・報告は遅滞なく
作業場の換気と装備
酸素欠乏危険場所の換気
・作業場は換気して空気を基準値に合わせる
・基準値は酸素18%以上
・硫化水素10ppm以下
・酸素中毒や爆発を防ぐ為、純酸素の使用はNG
酸素欠乏危険場所での装備
・換気が出来ない場合は空気呼吸器を装備
・酸素欠乏症の人を救助する際も空気呼吸器を装備
・転落の危険がある場所では墜落制止用器具等も装備
・墜落制止用器具(旧呼称:安全帯)等には命綱も含む
 でぃでぃ
でぃでぃ赤字は特に大事です!
酸素欠乏関連の既出論点
最後に酸素欠乏に関わる既出論点を整理します。
| 既出の論点 | 要否・頻度・内容 |
|---|---|
| 作業主任者 | 選任要 技能講習の修了 (第1種・第2種が存在) |
| 特別の教育 | 要 (第1種・第2種が存在) |
| 作業環境測定 | 毎日始業前・記録3年 第1種:酸素濃度 第2種:酸素・硫化水素濃度 |
| 定期自主検査 | - |
| 特殊健康診断 | - |
 おっさん
おっさん有害物質を発生させる訳ではないから定期自主検査と特殊健康診断はスルーでいいな。
試験対策の材料を揃えたので、過去問から酸素欠乏症等予防規則の問題をやってみます。
■問.酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)し尿を入れた事のあるポンプ修理で、これを分解する作業に労働者を従事させる場合、指揮者を選任し、作業を指揮させる。
(2)汚水を入れた事のあるピット内部の清掃作業に労働者を従事させる時は、第一種酸素欠乏危険作業にかかる特別の教育を受けさせる必要がある。
(3)爆発・酸化を防止するため酸素欠乏危険場所の換気ができない場合、労働者に空気呼吸器を使用させる。
(4)タンク内部その他通風が不十分な場所でアルゴン等を使用する業務に労働者を従事させる時は、酸素濃度が18%以上になるよう換気するか、労働者に空気呼吸器を使用させる。
(5)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業開始前に空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
誤っているものは(2)です。
 おっさん
おっさん選択肢の文章が長くても落ち着いて読んでいけばただの間違い探しだな。
 でぃでぃ
でぃでぃ慎重に・確実に…です。
 でぃでぃ
でぃでぃ次は粉じんの防止規則です。
粉じん障害防止規則の攻略
粉じん障害防止規則も、第一種 衛生管理者の試験において出題率50%前後の高い頻度で出題されています。
石や金属の微粉(粉じん)を吸い込んで肺の内部が繊維化したりと呼吸に関して重大な健康障害を引き起こします。
粉じん障害に関する定義などを整理します。
粉じん作業の例
1.土石・岩石・鉱物を掘削する
2.屋内でガラス製造の際、溶解炉に原料を投入
3.耐火物を用いた炉を解体する
4.屋内で手持ち工具で金属を研磨する
5.タンク内部等でアーク溶接をする
6.鋳物用の砂型を壊す
特定粉じん作業の例
粉じんの発生源が一定の箇所(特定粉じん発生源)である作業
1.屋内でセメント・フライアッシュ・粉状の鉱石や炭素粉・金属粉を袋詰めする作業
2.屋内に設置(据置)された研磨機・研磨材で金属を研磨・裁断・バリ取りする作業
参考リンク:フライアッシュ
特定粉じん発生源の措置
粉じんの飛散防止の為、以下のいずれかの措置を講じる
1.湿式型の削岩機を使用
2.湿潤に保つための設備を設置
3.密閉する設備を設置
4.局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設置する
 おっさん
おっさん粉じん作業と特定粉じん作業は別モノってのを理解しないとだよな。
換気・除じん・清掃
粉じん作業(特定粉じん作業以外)の屋内作業場は全体換気装置と同等以上の換気を出来るようにしておきます。
また、特定粉じん発生源の局所換気装置に設ける除じん装置は、粉じんの粒の大小などで除じん方式を分けると定められています。
| 粉じんの種類 | 除じん方式 |
|---|---|
| ヒューム (粒が小さい) | ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
| 粉じん (粒が大きい) | ろ過除じん方式 電気除じん方式 マルチサイクロン スクラバ |
清掃については、粉じん作業・特定粉じん作業の作業場は毎日1回以上の清掃をしなければなりません。
 でぃでぃ
でぃでぃヒュームの方が粒が小さいので高度な除じん方式を採用しなければですね。
粉じん障害関連の既出論点
最後に粉じん障害に関わる既出論点を整理します。
| 既出の論点 | 要否・頻度・内容 |
|---|---|
| 作業主任者 | - |
| 特別の教育 | 要 |
| 作業環境測定 | 6カ月毎・記録7年 空気中の粉じん濃度 遊離ケイ酸含有率 |
| 定期自主検査 | 1年毎・記録3年 局所排気装置 プッシュプル型換気装置 除じん装置 |
| 特殊健康診断 | じん肺健康診断 就業時・離職時※1 1年or3年毎※2 記録7年 胸部エックス線 |
※1:離職時は1年以上従事した場合
※2:じん肺管理区分による
 でぃでぃ
でぃでぃ…特定=フライアッシュと袋詰めのキーワードで試験は乗り切れる…
粉じん障害防止規則は2タイプの出方があります。まずは他の予防規則・防止規則と同じタイプからやってみます。
■問.粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置もしくは湿潤に保つための設備、またはこれらと同等の措置を講じる。
(2)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6カ月以内毎に1回、定期に空気中の粉じん濃度の測定を行い、結果を記録して7年間保存する。
(3)特定粉じん発生源にかかる局所排気装置に設ける除じん装置はヒュームを対象とした場合はサイクロンによる除じん方式である必要がある。
(4)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気または、これと同等以上の措置を講じなければならない。
(5)粉じん作業を行う屋内作業場については、毎日1回以上の清掃が義務付けられている。
誤っているのは(3)です。
もう一つのタイプの過去問もやってみます。
■問.次の粉じん作業のうち、特定粉じん作業に該当するものはどれか。
(1)屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
(2)耐火物を用いた炉を解体する作業
(3)屋内において、研磨剤を用いて手持ち式動力工具により金属を研磨する作業
(4)屋内において、フライアッシュを袋詰めする作業
(5)タンク内部において、金属をアーク溶接する作業
該当するものは(4)です。
 おっさん
おっさんフライアッシュだけ参考リンクがあったから何かあるとは思ったが。
 でぃでぃ
でぃでぃフライアッシュときたら特定粉じんだから…
 でぃでぃ
でぃでぃ次は石綿の予防規則です。
石綿障害予防規則の攻略
石綿障害予防規則は、試験で出題率は低めでしたが、最近は上がってきているので対策しておいた方が良いです。
規則から試験に出そうなものを整理します。
石綿関連・各種施設の管理
①作業場と休憩室は別の場所に設置する
・作業場には「試験研究のために少量の石綿を取扱う」場所も含む
②作業場での飲食・喫煙は禁止
・作業場の見やすい箇所に表示する
③作業場等の清掃は「1日1回以上行い」かつ「水洗い等で石綿が飛散しない方法」をとる
・容易に水洗いができる構造の作業場とする
④保護具(防塵マスク等)も水洗いする
 おっさん
おっさん石綿は飛んだらマズいから水で流せと。
石綿障害関連の既出論点
石綿障害に関わる既出論点を整理します。
| 既出の論点 | 要否・頻度・内容 |
|---|---|
| 作業主任者 | 選任要 技能講習の修了 |
| 特別の教育 | 要 |
| 作業環境測定 | 6カ月毎・記録40年 空気中の石綿濃度 作業環境測定士が実施 |
| 定期自主検査 | 1年毎・記録3年 局所排気装置 プッシュプル型換気装置 除じん装置 |
| 特殊健康診断 | 石綿健康診断 就業時・離職時 6カ月以内ごと 記録40年 胸部エックス線 |
 おっさん
おっさん石綿は作業環境測定と特殊健康診断の記録保存が40年だったな。
第一種 衛生管理者の過去問で石綿障害予防規則は選択肢一つ一つが長いので、落ち着いてゆっくり読みましょう。
■問.石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回・定期に作業環境測定を行うとともに測定結果等を記録し、これを40年間保存する。
(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として1年以内ごとに1回・定期に自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録しこれを3年間保存する。
(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回・定期に特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から 40 年間保存する。
(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要・従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から 40 年間保存する。
(5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出する。
誤っているものは(5)です。
 おっさん
おっさん読むのに疲れるなコレ…
 でぃでぃ
でぃでぃ割り切ってゆっくり読むしかないですね。
 でぃでぃ
でぃでぃ次は…ちょっとアレなやつです…
有害業務に係る衛生基準の試験対策
試験では複数の有害業務の予防規則・防止規則を跨いだ難易度が高い問題が出される事があります。
少し邪道ですが、最近の過去問で登場したものをピックアップします。
| 安衛則 | 対象・内容 |
|---|---|
| 581条 | 病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、 消毒、殺菌等適切な処理をした後に排出し、又は廃棄しなければならない。 |
| 584条 | 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、 隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。 |
| 585条 | 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所 又は硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、 かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 |
| 592条 | 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。) を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に当該作業場における空気中の ダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。 |
| 608条 | 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、 加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から 労働者を保護する措置を講じなければならない。 |
| 611条 | 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。 |
| 614条 | 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由が ある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。 |
赤字の部分は数字を変えて出題してくるものや、見慣れないキーワードです。
 おっさん
おっさん衛生基準っつーから労働衛生で出ると思ったら法令で出るのかよ…
第一種 衛生管理者試験で衛生基準についての問題が低確率で出ます。出ると難しいので対策しておきましょう。
■問.労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうはどれか。
(1)坑内における気温は、原則として、37℃以下にする。
(2)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じる。
(3)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が 0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示する。
(4)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設ける。
(5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回・定期に当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定する。
誤っているものは(3)です。
 おっさん
おっさん間違い探しだから最初に数字を睨んでみてもいいかもな。
 でぃでぃ
でぃでぃそれ、割とアリです。
 でぃでぃ
でぃでぃ防止規則と予防規則はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:労働基準法関連
【難易度:易】
労働基準法
(有害業務関連)
衛生管理者試験に向けた覚え方
ここからは労働基準法で有害業務に関連する内容です。
第一種 衛生管理者の試験では問10に固定で2つの論点:女性の就業制限等・有害業務の残業制限どちらかが出題されます。
学習範囲が非常に狭く難易度も易しいです。
 おっさん
おっさん最後に楽させてもらえるのか…
女性の就業禁止・制限される有害業務
有害業務の中でも女性に特に良くない業務への就業禁止や身体の状況による就業制限が定められています。
身体の状況は、妊娠中・産後1年以内・一般の3区分で整理します。
| 危険・有害業務 | 妊婦 | 産婦 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 坑内労働 | 要 配慮 | ||
| 重量物を取扱う 有害物を取扱う (鉛・水銀・クロム) | |||
| 著しい振動 (削岩機・鋲打機) | |||
| 5m以上の場所 (高さ・深さ) | |||
| その他の有害業務 (ボイラー・溶接等) |
表中で△が入っているところは、対象者が産後1年を経過するまでその業務に従事しない旨を申し出た場合は✕となります。
※妊産婦同様、18歳未満の男女も坑内労働・有害業務に就かせてはダメです。
 でぃでぃ
でぃでぃ実際は申し出て✕にして身体を休めるのが良いですね。
女性の重量物の取扱い
取扱う重量物の重さは年齢・作業の継続性によって上限が変わります。
断続作業・継続作業
・断続作業=取扱いは断続的
・継続作業=常に取扱う
女性の年齢と作業の断続/継続での重さ上限を整理します。
| 年齢 | 断続作業 | 継続作業 |
|---|---|---|
| 満16歳 未満 | 12㎏ | 8㎏ |
| 満16歳以上 満18歳未満 | 25㎏ | 15㎏ |
| 満18歳 以上 | 30㎏ | 20㎏ |
例)満18歳以上の女性は継続作業で20㎏以上の重量物の取扱いは禁止
 おっさん
おっさん男も同じように数値が決まってるけど、ここではスルーで良いな。
第一種 衛生管理者の試験では、ここまでの内容だけで出題される事がよくあります。
■問10.労働基準法に基づき、全ての女性労働者に就業が禁止されている業務は次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取扱う業務
(3)20㎏の重量物を継続作業として取扱う業務
(4)削岩機等、身体に著しい振動を伝える機械器具を用いる業務
(5)病原体によって著しい汚染のおそれのある業務
該当するのは(3)です。
 おっさん
おっさんめっちゃ簡単じゃねーかコレ。
 でぃでぃ
でぃでぃもっと簡単なバージョンが出る時もありますが…
有害業務の時間外労働の制限
こちらは男女・年齢問わずの内容です。
坑内労働と有害業務は、1日2時間以上の時間外労働(残業)をしてはダメという内容です。
ただし、以下の3つは対象外です。
有害業務で1日2時間以上の残業OK
1.著しく多湿・湿潤な場所での業務
2.著しい精神的な緊張を伴う業務
3.病原体によって汚染の恐れのある業務
 おっさん
おっさんこれだけで1問の対策になるのか…?
 でぃでぃ
でぃでぃそーなんですよ…
それでは早速、過去問をやってみます。
■問10.次のAからDの業務について労基法に基づく36協定を結んで労基署長へ届出をしたとしても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せはどれか。
A:病原体によって汚染された物を取扱う業務
B:腰部に負担のかかる立ち作業の継続業務
C:多量の低温物体を取扱う業務
D:鉛の粉じんを発散する場所における業務
(1)A・B (2)A・C (3)B・C
(4)B・D (5)C・D
該当するのは(5)です。
 おっさん
おっさんここまでやってきた有害業務の中で対象外を探すだけか。
 でぃでぃ
でぃでぃこっちは簡単すぎる分、問10は女性の就業制限の方がよく出ますけどね。
 でぃでぃ
でぃでぃ関係法令(有害業務関連)はここまでです!
衛生管理者-関係法令 有害:おわりに
 おっさん
おっさんふー…疲れたぞ。
 でぃでぃ
でぃでぃ見慣れない言葉ばっかで疲れましたよね。
 おっさん
おっさん普段のんびり生きてると関わらない事が一気に出て来たな。
 でぃでぃ
でぃでぃそうなんです。その中で法令だけを見るのって難しいです。
 おっさん
おっさん試験対策するには関係法令だけじゃなくて労働衛生もやって自分に落とし込んでけって話だよな。
 でぃでぃ
でぃでぃです。関係法令のページだけ何度も見るよりは、衛管の全ページを順番に繰り返し見るといいかもですね。
 おっさん
おっさんこれは何回か全範囲をローラーかけないと試験に合格できる気がしないな…
 でぃでぃ
でぃでぃわたしもそうでした。少し休んだら労働衛生(有害業務)に行ってみましょーか。
 おっさん
おっさんすまん、もう少し休ませて…
第一種 衛生管理者の試験対策のうち、関係法令(有害業務に係るもの)はここまでです。
次のページは労働衛生(有害業務に係るもの)前半です!
■衛生管理者 ページ一覧
①:衛生管理者の概要
②:関係法令-有害業務(前半)
③:関係法令-有害業務(後半) ◀◀ NOW
④:労働衛生-有害業務(前半)
⑤:労働衛生-有害業務(後半)
⑥:関係法令-一般業務と共通
⑦:労働衛生-一般業務と共通
⑧:労働生理(前半)
⑨:労働生理(後半)